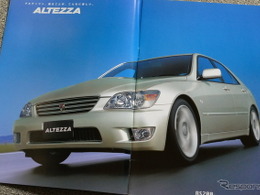2025年に消防事業が40周年を迎える、ヤマハ発動機のグループ企業のひとつ「ヤマハモーターエンジニアリング」(YEC)。新たに消防ブランド『X(クロス)』を立ち上げ、自社開発した火災現場向けの加納式電動アシストホースカー『X-QUICKER(クロスクイッカー)』の各地の消防署での採用と稼働も始まっている。そんなヤマハモーターエンジニアリングとは一体どのような会社なのか、なぜ消防事業なのか、そしてバイクとの関連性はあるのか。
消防事業に携わり、電動アシストホースカーの開発をおこなうメンバーに話を聞いた。
■インタビュー参加メンバー(敬称略)
事業企画推進部 事業グループ
開発プロジェクトリーダー
藤井勲
事業企画推進部 事業グループ
グループリーダー
杉山和弘
モビリティ開発部 CAE実験グループ
主事
畑島康佑
◆白バイから工場設備まで、「RZ50」も手がけたヤマハモーターエンジニアリング

----:まず初めに、ヤマハモーターエンジニアリングの成り立ちと役割を教えてください。
杉山:弊社はヤマハ発動機の100%子会社で、設立は1980年です。ヤマハが持つ技術を独立した形で磨き、社会の中で新しい価値を創造するという目的を掲げています。当初は、ヤマハの中で開発の一部を担う小さな規模でしたが、現在は多種多様な分野において、製品の企画から開発までを一括して受託。ニッチながらも社会への貢献度が大きい商材を手掛けています。
----:ホームページを拝見しましたが、製品は本当に多岐に渡りますね。白バイや赤バイ、電動アシスト自転車、レース用キットもあれば、工場の設備やロボット、システム開発までさまざま。RZ50(1996年)などは、ほぼすべてを御社が担っていたと知りました。そんな中でも異質にも思えるのが消防関連の製品ですが、これはどういった経緯で始まったのでしょう。

杉山:40年ほど前にさかのぼりますが、東京消防庁からヤマハ発動機を通し、消火ホースを運んだり、伸ばしたりするための資機材を作りたいという相談を受け、「電動ホースレイヤー」と呼ばれるものを完成させました。それを評価して頂き、消防用の赤バイや投光器等の開発にもつながったのです。
----:電動アシストホースカーのクロスクイッカーは、いつから開発が始まったのでしょうか。
杉山:2019年頃です。ホースカーには、人が乗って運搬する乗用タイプ(ナンバー取得は不可)があるのですが、火災現場までは消防車に積載して運びます。しかしながら、消火活動のスタイルが変化する中、ホースカーのコンパクト化と軽量化が求められるようになったことが開発のきっかけです。
藤井:たとえば都市型の火災では、小型の消防車が求められる一方、迅速な初期消火のために、800~1000リットル程度の水を水槽に入れて積んでおきたいという、相反する要望があります。乗用タイプだと消防車の積載スペースを占める割合が大きくなりがちで、また消防車自体にも耐用年数があるため、ホースカーの改良や更新も常に平行して行う必要があるんです。
◆「人機官能」や「人機一体」の思想を受け継いだ

----:ホースカーは実際の現場でどのように使うのですか?
藤井:見た目からご想像頂ける通り、リアカーのように人が引っ張る構造です。消火ホースは通常1本あたりの長さが20mあり、これをホースカーの荷室に10本、つまり200m分を収納。それによって、火災現場と水源を繋ぐのが最大の役割です。
----:水源が遠い、山林のような場所だと大変な距離になりますね。
藤井:はい。ホースの重さは約8kg/本です。人力の場合、屈強な消防隊員なら6本ほど背負うことになりますが、その本数がさらに稼げることに加えて、電動アシストによって隊員の負荷を軽減。また、必要であればホース以外の機材も運搬できます。
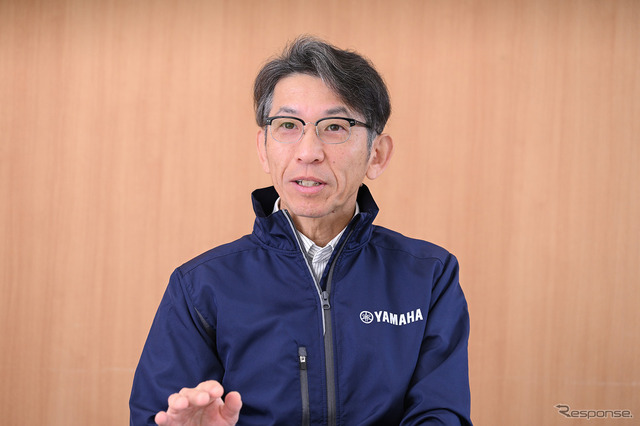
----:電動ホースカーを手掛けているメーカーは他にもいくつかあるようです。クロスクイッカーならではの特徴はなんでしょうか。
杉山:まず、バイクのようなスロットルではなく、持ち手を引く力をセンサーが感知してアシストが働くこと。そして、14インチ(タイヤ外径512mm)の大径ホイールの採用によって、段差や悪路での高い走破性が挙げられます。
----:スロットルの方がヤマハの技術を転用しやすかったと思うのですが?
杉山:消火という1分1秒を争う現場において、スロットルを回すという行為は、取り回しやコントロール性の面でネックになることがあります。その点、クロスクイッカーは、「引く」というシンプルで直感的な操作に追従し、ホースカーが前進する動きと人の体の動きが一致します。その意味では、ヤマハがしばしば提唱する「人機官能」や「人機一体」の思想を受け継いでいると言えます。

----:装備のいくつかは、バイクで見慣れたものが使われていますね。
畑島:ホイールやタイヤ、ブレーキなどは弊社のスクーター部品を流用していますし、グリップやスイッチボックスもそうです。あと、役割は異なりますが、センサー部分に装着しているステアリングダンパーも二輪用です。
藤井:隊員の方の中にはバイク好きも少なくないので、「これって、あのバイクのパーツですよね」と、ひょんなことで盛り上がることもあります。

◆スイッチひとつ、あとは引くだけで性能を発揮できるシンプルさ
----:作り込みに関して、もう少し詳しくお聞かせください。
畑島:開発のベースに二輪の技術があるのは間違いありません。もちろん、二輪の測定方法や評価基準をそのままスライドさせられませんが、頑強さと軽さのバランスはバイクの車体設計に通じるものがありますし、アシストの制御に関しては電動アシスト自転車等の知見も取り入れつつ進めてきました。
----:ホースカーに求められる制御とはどんなものでしょうか?
畑島:パワーとスムーズさの調整によって、いかに自然に扱えるかですね。その点に関してはかなりこだわり、バイクの電子制御スロットルとも電動自転車のペダルとも異なる、ホースカーに特化した独自のロジックを専門の制御部門に組み込んでもらいました。

藤井:ただし、こうした製品の難しさは、世に送り出した後にどのように使われているのかを、なかなか見られないことにあります。火災現場に帯同するわけにもいかないので、消防の方々と頻繁に会い、その声をいかにフィードバックできるか。そこが重要なポイントです。
畑島:そのため、試作段階のバイクに一般のユーザーが乗る、というケースはまずないことですが、クロスクイッカーに関しては、かなり初期の時点で隊員の方達に試してもらい、幾度も仕様変更を繰り返してきました。
藤井:企画が立ち上がった時は、パワーモードを付けるとか、操作手順に幾通りかのパターンを設けるとか、さまざまなアイデアがあったのですが、現場をよく知る方々に使ってもらったことで「やっぱりシンプルが一番いい」ということになりました。だったらスイッチひとつ、あとは引くだけで性能を発揮させられるように注力。結果的に完成したのが、現在の仕様です。

----:実際に引かせてもらいましたが、総重量が200kg超とは思えない、滑らかな動き出しでした。
畑島:開発は当然アシストありきで進めるのですが、スムーズすぎて、いつの間にか忘れているんですよね。たまにスイッチを切った状態で引くと、その手応えに自分で驚きます(笑) 自然な操作フィーリングには、自信を持っています。
◆安心安全を守るヒーローの手助けになるものを届けたい
----:こういった製品の場合も、最初に開発コンセプトを掲げたりするものですか?
杉山:企画の時点で明確に決めました。火災という切迫した状況なので、まず「迅速」であること。簡単な操作はそのためのものです。次に、途中でトラブルが発生したり、現場にたどり着けないようなことがあってはいけないので「確実」かつ「安心」であること。パワフルさや走破性の高さ、バッテリーの持ちのよさ(満充電で約20kmの連続走行)等がそれにあたります。

藤井:先程申し上げた通り、我々が直接火災現場に出向くわけにはいきませんが、「迅速」、「確実」、「安心」のため、可能な限り、実際の現場を想定した開発を行っています。バイクの耐久テストもそれなりに大変ですが、ホースカーは我々自身が引いたり、走ったりしながらデータを蓄積しています。消防隊員はそもそもタフな肉体の持ち主ですが、このアシスト機能によって、その力をさらに高めて頂けるなら開発のやりがいがあります。もちろん、理想はホースカーの出番がないことが一番ですが。
----:ヤマハモーターエンジニアリングとして、今後どのようなものづくりを進めていくのか。ビジョンがあれば、お聞かせください。
杉山:特装製品を担う我々の部門は、「Best Value for Heroes ~技術と創造力でヒーローたちを支え共に戦う頼れる相棒~」というスローガンを掲げて活動しています。消防関連機器はその最たる例で、災害現場の最前線で尽くす方々だけでなく、医療や介護、育児、交通といった、あらゆる場面で安心安全を守るヒーローの手助けになるものを届けたいと考えています。ヤマハ発動機のスローガンが「Revs your heart」で、こちらがお客様の暮らしを豊かにするものだとすると、我々は製品やシステムを通じて、それを支える。そういうスタンスでこれからも開発に取り組んでいきますので、エンジニアリングの面で必要として頂けるなら、どなたでもお声がけください。
----:ありがとうございました。今後の製品も楽しみにしています。


















































![音の変わり幅が特に大きいのは“アンプDSP”! 満足度も高し[初めてのカーオーディオ“とっておき”をプロが提案]](/imgs/p/h_qLlAraJVMaGW9nq6wZtJmorKdlpaSjoqGg/127250.jpg)